
第2回勉強会報告
科学者を魅力的に見せるためのあの手・この手
講師:日本科学未来館 科学コミュニケーター 橋本裕子氏、三ツ橋知沙氏、森田菜絵氏
-
-
科学を楽しく、面白く伝えるための手法や考え方を学ぶ勉強会を平成21年9月13日(日)に発生・再生科学総合研究センターにて開催しました。第2回となる今回の勉強会では、日本科学未来館から科学コミュニケーターの橋本裕子さん、三ツ橋知沙さん、デザイナーの森田菜絵さんをお招きし、プレゼンテーションの方法やノウハウを中心に講義して頂きました。講義の形式は、参加者全員による自己紹介や積極的な質疑応答など、受講者が能動的に参加出来るような雰囲気作りをされていました。また、講義が始まるまでの合間に、三ツ橋さんによる前説もあり、会全体の雰囲気が和やかになりました。三ツ橋さんは司会やファシリテーターの経験が豊富で、場を盛り上げ引っ張っていくことに非常に長けていました。受講者は、学生や研究者に限らず、教員や会社員の方々も参加して頂き、前回同様様々な立場・分野の人々と交流できる機会となりました。
当日の概要
第2回勉強会を開催
CDB広報国際化室おもろい研究者創出プロジェクト勉強会第2回を開催しました。
日時・場所
平成21年9月13日(日)
14:00~16:00
理化学研究所
発生・再生科学総合研究センター
A棟7Fセミナー室
参加人数
24名

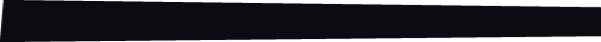

<日本科学未来館について>
東京のお台場にある国立の科学博物館で、スローガンは「科学がわかる、世界がかわる」。科学技術の新しい知識を得ることで、他の物事も今までとは違う新しい見方で捉えることが出来るというメッセージが込められています。未来館には約50人の科学コミュニケーターが在籍しており、大学などで科学技術を学んだバックグランドを持つスタッフの他、デザインや制作を専門に取り扱っているスタッフもいます。科学館は市民に科学技術を伝えるだけでなく、市民の感覚や所見を研究者にフィードバックするという双方向のコミュニケーションを実践しています。また、ファシリテーション講座や情報コーディネーション講座、プレゼンテーション講座を開催し、科学コミュニケーターの育成にも取り組まれています。
日本科学未来館HP:http://www.miraikan.jst.go.jp/

<講義概要>
科学コミュニケーションとは? 講師:橋本さん
科学を市民に伝える手段として3つのモデルがあり、トピックやターゲット、目的によって最適なモデルを選択する必要があります。
欠如モデル・・・科学技術に対する市民の知識が欠如しているため、専門家がその部分を埋める。
一方向的 知識拡散型
対話モデル・・・専門家と市民が持つ知識の質は異なるが、意見の違いを理解し、対話を深める。
双方向的 合意形成型
文脈モデル・・・科学技術の知識や重要性を状況や文脈の中で捉え、双方の知恵を尊重し、
対等な立場で議論する。 双方向的 倫理や政治も扱う。
また、特に研究者が一般向けイベントに参加した際陥りやすい点として、専門用語を用いて説明する、受動的で断言しない表現を使う、スライドを使用するときに、発表時間内に収まりきれない程の情報を詰める、英語表記やグラフ・表といった学会で使用したスライドを使いまわすなどの特徴を指摘されました。これらは研究者同士では良いですが、市民向けには非常にわかりにくいプレゼンになってしまいます、という注意が。(た、確かに身に覚えが(?)。)
おもろい研究者になりませんか勉強会事務局スタッフ 松田一起
(発生・再生科学総合研究センター 生殖系列研究チーム)
<参加者へのアンケート結果>
Q1. 今回の勉強会の感想をお答えください。
・全員が自己紹介したことで、講演者や他の参加者との距離が近く感じられた。
・コンテクストの違う人(専門外の人)とのコミュニケーションについて理解が深まり、非常によかったです。
・科学をもっとクリエイティブなモノと捉える観点を持ちたいと思った。
・今までプレゼンがうまくできなくて悩んでいたが、対策・改善点をクリアにすることができてよかった。
・異文化の音楽やアートとのコラボレーションによる効果がとても大きかったことに驚きました。
・サイエンスを知らない人と実際どのように接点をもらったら良いのかヒントをたくさんいただきました。
・科学コミュニケーションの最前線で働かれている方の話が聞けて良かったです。
・未来館で面白そうなイベントをたくさんされているのを知り、近くに住んでいたら参加してみたいなと思いました。
Q2. 今回の勉強会で得られたことをお答えください。
・断言するような言い方は不正確な表現だと思って使いたくなかったが、混乱を避けるためにも使った方が良いことが分かった。
・周りの人に日頃から自分の研究を説明する練習をすべきだと思った。
・自分が思っているよりも、一般の人とコミュニケーションができていないことに気がついた。
・いかにして、科学の興味を無い人に科学を伝えるかについて学ばせて頂きました。
・聞く側の身になってプレゼンすることの大切さ。暗黙の了解で相手もわかっているだろうといった部分もきちんと説明することでより伝わる。
・普段、必要に迫られて、何気なく行っているプレゼンテーションですが、その基本を見直すことができてよかったです。
・言葉の選び方であんなにも結果が異なると思いませんでした。今後はプレゼンのスライドだけでなく言葉の表現方法にも注意したいと思いました。
・科学コミュニケーションの分野でいろいろな取り組みがされているなと改めて知りました。自分も今回もらった知識を役立てていきたい。
・プレゼンテーションに対して無形のコツや伝承、マネではなく、理論的に手法を勉強する必要があることが分かった。また、一般の方に対するアプローチの必要性を感じた。
Q3. 今後このような勉強会に参加したいですか。
Yes 22人No 0人
Q4. あなたは科学を広く伝えることの必要性を感じますか。
Yes 21人No 1人
<Yesの理由>
・自分が興味を持っており、そこで学んだ思考のフレームワークや気をつけるべきポイントが人生の他のところでとても役立つことを実感しているから。より多くの人が毛嫌いせずに学んだ方がいいと思います。
・科学に対して食わず嫌いな一般の人達に新しい価値観を持って、もっと楽しんでほしいから。
・科学技術も一つの文化であり、他の文化と同様に広く楽しみ理解することができる対象だから。
・科学技術立国を目指すのであれば、欧米並みかそれ以上に社会として科学を受け入れておく必要があると感じます。
・理系離れといわれるが、勉強というより科学を興味の対象にしてほしい。特に子ども。
・仕事として、社会活動の一部として科学を研究しているので、その成果や活動内容は社会に還元する必要があると思います。
・各分野のリーダーが他分野や一般の人に分かりやすく、その分野のおもしろさを伝えることでさらなる発展が可能になる。
・当たり前に使われている科学技術の正しい使い方を後世に伝える必要があるため。
・誤解が多すぎる。人と人がはがれていってしまいそう。
・科学は社会や生活に重要なので、よりよい技術を世間に浸透させるためにも知識からくる安心感は必要であると思います。
・科学とは日本が生き残る道。
<Noの理由>
・研究所としてやるべきことがどこまでかというのは考えるべき。おせっかいすぎるのもどうか。
<どのような立場の人が伝えるべきだと思いますか。>
・科学が本当に好きな人がするべきだと思う。
・既に科学を楽しみ、理解している人が伝えるべき。
・科学に携わる者(研究者自身)とそれをサポートする人。
・研究費の多くが税金であるため、研究者本人が伝えるのが望ましい。
・研究者、教師ももちろんですが、親(周りの大人)が少しでも伝えられるようになったらいいと思う。
・立場に関係なく、伝えるのではなく“話せる”と良いのではないでしょうか。だだし、一般の方が興味を持ってもらうとっかかりとして、ネームバリューは大切だと思います。
・包容力がある人が伝えるべき。
・研究を実際にやっている人が伝えるのが大切だなと思います。伝えるなかで一般の人の意見とか、認識のギャップとかを知ることができると思うので。

<参加者による自己紹介>
橋本氏、三ツ橋氏からの簡単なイントロがあったあと、まず冒頭に参加者全員一分程度で自己紹介をしました。何の事前予告もなくいきなり「振られた」ことになりますが、皆さん饒舌な方が多く面白い(?)自己紹介でした。この勉強会に参加した経緯や目的などを互いに共有できるよいきっかけとなりました。



プレゼンテーションの基本構造 講師:三ツ橋さん
なぜ、科学コミュニケーションは難しいのでしょうか。それはコンテクストの違いから生じるギャップがあるためです。コンテクストとは、「阿吽の呼吸、暗黙の了解」といった状況や背景によって言葉や表現を理解する、コミュニケーションするための共通基盤のことです。より効果的なプレゼンテーションをすることで専門家と市民とのギャップを埋めていきましょう。
-
1.イントロ:導入と概要。相手をひきつける。
-
2.ボディ:結論の根拠や具体的な内容。順序に配慮し、相手 の興味を高めていく。
-
3.コンフルージョン:2.をふまえて1.を導く。テイクホームメッセージを届ける。
また、言語だけでなく非言語(人体、動作、目、周辺言語、沈黙、身体的接触、対人的空間、時間、色彩)も意識すると表現の幅が広がります。フレーミング効果を活用するのも有効です。フレーミング効果とは、数理的に全く同一の事象であっても表現方法により心理的な解釈が異なることを言います。
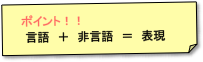
科学者を素敵に見せるには? 講師:森田さん
日本科学未来館では、科学と音楽・アートを組み合わせて表現するなどユニークな取り組みがなされています。このようなイベントに参加した研究者や音楽家、芸術家は、分野が違っても好きなものへの情熱や純粋な想いといった共感できる部分もあり、お互いを理解し合うことが出来たようです。普段のイベントには高齢者や科学好きな人が多く参加されますが、例えばラップと科学、など、これまでにはなかった表現ジャンルの組み合わせによって、今までとは違った客層を呼び込み科学の面白さを伝えることができます。
また、伝えたいエッセンスを抽出して、別の言葉に置き換えてみることも大切です。そうすることで、何か新しいものや科学者以外の人が共感できる“詩的”な部分が生まれるかもしれません。
森田さんが手がけたプロジェクト
Birthday:http://www.miraikan.jst.go.jp/sp/birthday/index.html
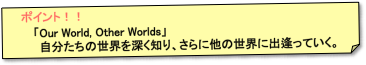
おもろい研究者になるためには?
では、どうすればおもろい研究者になれるのでしょうか。何が必要なのですか。
【かっこいい研究者になること】と、橋本さん。「かっこいいとは、科学を社会の中で俯瞰(ふかん)的に捉えること、新たな世界観を具体的事象で示すことができる人のことです。話を聞いている人への配慮も忘れず、情熱を持って取り組めることも大事です。」
【夢をキラキラと語れること】と、三ツ橋さん。「好きな気持ちは全身から染み出ます。そのキラキラが周りに伝わることで、何かが変わっていくと思います。」
【科学以外にも面白がれる余裕を持つこと】と、森田さん。「あることを深く追求すると、他分野で同じように追求している人と響き合うことができます。インスパイアしたりされたりするような体験をしてほしいです。」
科学の魅力を伝えるなら、その人自身の魅力も必要なのですね。確かに、魅力的な方の講演は、どこか魅入られるものがあります。その境地には簡単に辿り着くことはできないでしょうが、少しずつでも近づいていきたいものです。そして、今こそこのような科学者・研究者が求められているのです。
あなたも、おもろい研究者になりませんか?