Column
役に立つ研究
西川伸一(幹細胞研究グループグループディレクター)
最近役に立つ研究を心がけよという号令があちこちから聞こえてくる。ちょっと前には、日本も応用科学一辺倒から、欧米並みに基礎科学に貢献できる成熟した科学技術行政をとるべきとの意見もあったのだが、不況の到来と共にこんな声はどこかに消えてしまった。しかし、世界を周ってみるとこれは日本に限った現象ではなく、国の政策として何かが語られるとき、欧米でも研究成果応用への道筋を示すべしとの声が大きい。これに対し、個人の興味に基づく研究こそ真の研究で、役に立つなど考えること自体が間違いであると声を上げる研究者も日本には多い。
冷静に見つめてみれば、役に立つ研究という主張には問題が多く、注意が必要だ。まず、研究者側の本能的な反発を買う。やろうかなと思っていることを、他人から改めて命じられるとやる気が失せることは誰もが経験しているはずだ。多分だれも役に立たないことを願って研究することはない。もし、各人の努力が人の役に立つのなら、喜ばしい限りだ。なのに、わかっていることをことさら言われると、思わず反発したくなる。
次の問題は、人の役に立てという目的設定があまりにも漠然としていることだ。糖尿病の治療に役立つことは十分具体的な目標だが、人の役に立つという目標には具体性がなく、精神論に近い。実際、それぞれが行っている研究が人の役に立つのかと抽象的に問われたとき、どれだけ正確に答えられるだろうか。たとえ糖尿病について研究していたとしても、それが人の役に立つか最後までわからないことが多い。長年かけた研究が、結局多くの人を死に追いやっただけで終わることすらあるだろう。まして役に立つことを最初から目標に掲げて具体的な研究を構想することは不可能ではないだろうか。
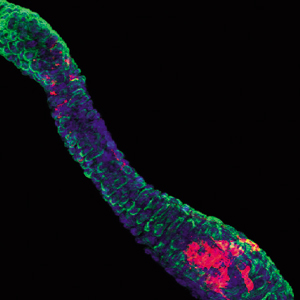
しかしこの掛け声が精神論に過ぎないとしても、精神論が持ち出される背景に流れている苛立ちを科学者側もよく理解する必要がある。当然、その一つには経済的背景がある。現代の科学は金食い虫だ。だから見返りを期待しない科学振興などほとんどありえない。実際、日本政府が2000年に始めたミレニアムプロジェクトも、バブル経済が破綻した後の長年にわたる不況に対する一つの政策として進められた。経済をはじめ国の重要問題は科学技術を通してしか解決がないという近代国家の思想的伝統に基づく政策だ(富国強兵を資源なしで実現するとしたら何が必要かを考えてみればよい)。
しかし、この近代国家の伝統は何も今に始まったことではないし、日本に特殊なことでもない。極めて現代的な背景として気になるのが個人の原子化問題である。日本を始め多くの先進工業国では、個人の自由の拡大と、国家や宗教といった絶対的な基準の喪失、そしてその結果社会の連帯が失われ個人の原子化が進むという事態が進行してきた。実際、現在の社会問題の多くが連帯の欠如と自己中心主義に起因すると考えられている。例えば、最近のライブドア事件やニート問題はこの典型である。その結果、社会全体にこのような個人の原子化状況に対する苛立ちが満ち溢れている。そんな中、「個人の興味でやる研究が重要で、役に立つ研究などは間違いである」という言明は必ず誤解される。それが、科学研究の重要な一面を言い当てているにせよ、科学者とはなんと自己中心的な特権階級であるかという印象を与えるはずだ。税金で支えられているのだから、誤解を生まないよう口を慎め!などと言うつもりはない。研究そのものは個人の興味に基づくにしても、それが他の人間とどのように関わり連帯しうるのかを考える想像力を持つべきではないかと言っている。私は、科学は必ず技術を生み出し、それが是非を問わず将来に大きな影響を与えると思っている。そして私たち人間が生き物である以上、生物に関わる研究の全ては人間の生命現象と関わる。だとすると、役に立つ研究など真っ平ごめんと言わないで、自分の活動を通して、これまで知らなかった誰かと連帯できないかなどと考えてみてもいいのではないだろうか。今、研究所や大学は一般公開や、様々なコミュニケーション活動を通して連帯を図ろうとしている。ただ、まだまだ、個人の発意に基づくというよりは、組織レベルの取り組みだ。これに加えて、もし研究に携わっている一人ひとりが、自分の研究が自分以外とどんなかかわりを持つのかちょっと想像をめぐらせるだけで、科学の世界からまた新しい風が吹くのではないだろうか。期待したい。


